リカード・モデル
| 経済学 |
|---|
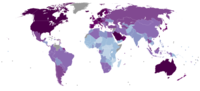 地域別の経済 |
| 理論 |
| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |
| 実証 |
| 計量経済学 実験経済学 経済史 |
| 応用 |
| 公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |
| 一覧 |
| 経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |
| 経済 |
|
|
|

リカード・モデル(英: The Ricardian model)は、国家間で各産業の生産性が異なることが理由で国際貿易が起こることを説明し、さらに貿易開始によって国の厚生が改善することを示す理論モデルのこと[1][2]。1772年生まれのイギリスの政治経済学者、デヴィッド・リカードが提示したモデル[1][2]。
歴史的背景
デヴィッド・リカードは27歳のとき、アダム・スミスの『国富論』を読み、そこで提示されていた様々な概念を応用してリカード・モデルが構築されるに至った。 リカード・モデルの原型とも言えるアイディアは1817年出版の『経済学および課税の原理』 に記述されている。そこには、地代の理論、労働価値の理論、そして比較優位の理論について記述されている。 リカードは、『国富論』を読んでから 10 年後に最初の経済論文を書き、過剰な貨幣供給がインフレーションを引き起こすというマネタリズムの理論の提起者としても知られている[1]。
モデルの概要
国際貿易のモデルであるリカード・モデルは、国が貿易を開始すると各国が比較優位産業に特化し、国全体の生産性が改善し、厚生が改善することを示す[2][3]。
ルディガー・ドーンブッシュ、スタンレー・フィッシャー、ポール・サミュエルソンは、連続的な空間に財が無数に存在する経済で、どのように比較優位産業が決定されるのかについて考察している[4]。
脚注
[脚注の使い方]
- ^ a b c Henderson, David R. "David Ricardo." The Fortune Encyclopedia of Economics, 1993.
- ^ a b c Fusfeld, Daniel R. "Ricardo, David." The World Book Encyclopedia, 1990 ed., 1990.
- ^ Bernhofen, Daniel M. (November 2005). “Gottfried Haberler's 1930 Reformulation of Comparative Advantage in Retrospect” (英語). Review of International Economics 13 (5): 997–1000. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9396.2005.00550.x.
- ^ Dornbusch, R.; Fischer, S.; Samuelson, P. A. (1977). “Comparative Advantage, Trade, and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods”. The American Economic Review 67 (5): 823–839. https://www.jstor.org/stable/1828066.
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本概念 |
| ||||||||||||
| 理論・議論 | |||||||||||||
| モデル |
| ||||||||||||
| 分析ツール |
| ||||||||||||
| 結果 |
| ||||||||||||
| 貿易政策 |
| ||||||||||||
| トピック |
| ||||||||||||
| 近接分野 | |||||||||||||
| Category:国際経済学 Category:貿易 Category:国際経済学者 | |||||||||||||








